西スポオリジナル!「やさしい競輪」コーナー&キャラ紹介はこちら
Q:地域ごとにラインを組むのはどうしてですか。いつからそうなっているのかも教えてほしい。
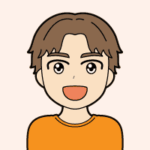 初~中級ちゅうた
初~中級ちゅうたレースでは普通いくつかのラインに分かれていますよね。同じ都道府県や、九州とか近畿とかの地区ごとに選手が並んでますけど、何か決まりとかあるんですか。強い人同士で組んだ方が有利な気がするし、仲良しの人で組んだりしてもいいんじゃないかって思ったんですけど
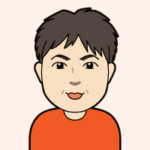
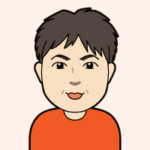
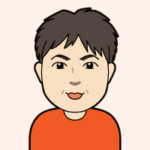
別に決まりとかはないんだけどね。ラインは、協力してみんなでいい着を取ろうという意識で形成される。同じ都道府県(支部)だと一緒に練習したり、プライベートでも仲良くしたりすることで仲間意識が芽生えて、一緒に勝ち上がりたくなる、ということで自然とそうなったんだろう。
その延長で、同支部でラインができなければ同地区同士、その次に隣の地区との連係-という感じかな
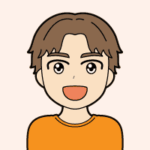
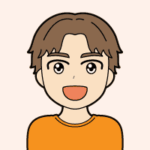
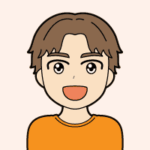
よく知っている同士なら、ダッシュがいいとかお互いの特徴を知っているし、チームワークも良くなるってことですね。地域以外でラインを組むことってないんですか
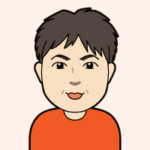
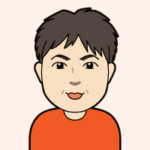
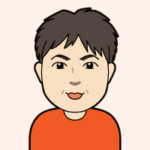
別地区でも競輪学校(117期以降は「選手養成所」)の同期とは仲がいいことが多いから、機会があればラインを組みたいというのもある。いわゆる「同期ライン」だね
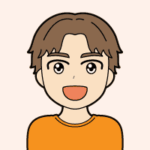
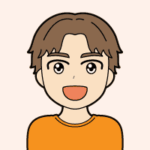
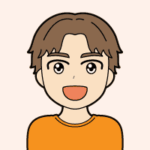
なるほど、お互いをよく分かってそうですしね。
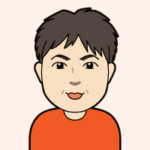
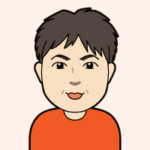
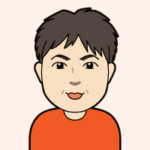
いつから地域で並ぶようになったのかを60代の元競輪選手に聞くと、以前は地域的なラインはあまりなく、選手の「格」で並んでいたらしいよ。ちゅうた君が言ってた「強い者同士」のパターンだ
一番強い自力選手には地元の主力の追い込み選手(自力選手の後ろで最後に逆転を狙うタイプ)が付く、2番目の自力型にはそれ相応の追い込み選手が付く、といった感じで並びが形成されていたそうだ。新聞記者もファンもその並びを予想して車券を買っていたみたいだね
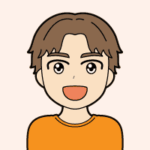
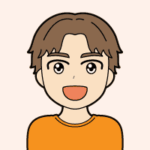
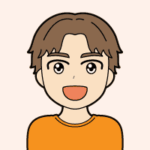
へー、地域と違ってパッとわかんないから、今よりも難しかったかもですねー
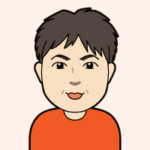
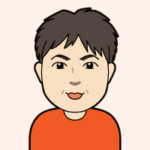
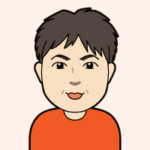
ちょっと昔話になるけど、1980年ごろに圧倒的なダッシュ力を誇った中野浩一(福岡・35期)が登場。今もテレビの解説でよくお見かけする、世界選手権スプリント10連覇のスーパースターだ。
その中野を封じるために東京と千葉の主力選手が連係して「フラワーライン」を形成したことは有名。ただこれも、「房総フラワーライン」という道路で街道練習をしていたという意味で、直接「ライン」とは関係がない集団だったんだけど、一緒に練習をすることで、中野に対抗するための戦術として実際にラインを組むことになったんだ。
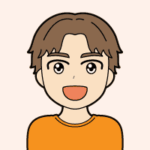
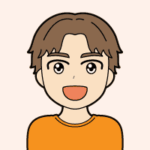
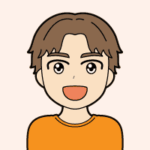
戦術を変えさせちゃうなんて、中野さんはほんとにすごかったんですね
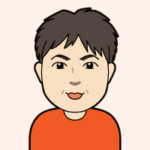
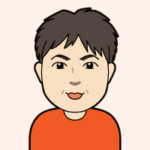
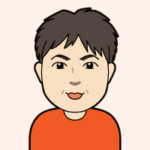
他の自転車トラック競技でも、チームスプリントやチームパーシュートなど、風の抵抗を考えながらチームで縦に並んで戦うよね。ツール・ド・フランスに代表されるようなロードレースでは、チームのエースを勝たせるために他の選手が交代で先頭に立ってエースの体力を温存する
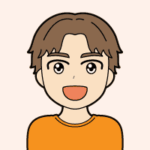
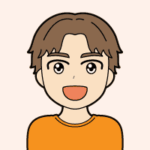
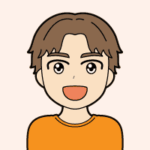
スピードに乗るほど風がきつくなりますもんね。チーム力って大事!
【用語解説】
・フラワーライン 山口国男(東京・24期)と弟の山口健治(東京・38期)、吉井秀仁(千葉・38期)ら、東京と千葉の練習仲間で構成。数多くのビッグレースのタイトルを獲得した。
・チームスプリント 3人1組(3周)で戦うタイムトライアル。1周回ごとに先頭選手が外れてゆき、最後の1人によるタイムで競う。女子は2人(2周)で行われていたが、2021年からは3人となった
・チームパーシュート 2チームで対戦する、個人追い抜きの団体版。1チーム4人で編成して4キロを走り、ゴールするときの3番目の選手のタイムを計測して勝敗が決まる。4人が順番に先頭を交代しながらレースを進める
- 「差し」「捲り(まくり)」の違いは? 競馬やボートと違う?
- 審判塔も赤ランプも消える? 競輪の審判員はどこへ
- 出走表の決まり手の数字の読み方は? 予想にどう使う?
- 競輪は急に止まれない!? 競走用自転車は通常のものとは何が違う?
- GⅠとかFⅠとかレースの格付けの意味は?
あなたの質問・疑問をお寄せください 採用者には記念品進呈!
↓ 受付フォームもこちらから ↓
